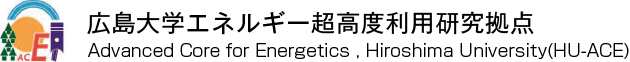HU-ACEニュースレターVol.22 を発行しました。(Click)
Author Archives: AsanoHiroko
第69回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第42回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2018年11月14日(水)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部109講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 D2 Rahmat Iman MAINIL
1.「高温圧縮水中のグリセロアルデヒド分解反応モデル 」
レトロアルドール縮合を受けているグリセロアルデヒドは、高温(350〜450℃)および高圧(25MPa)の水の下で処理されていました。本研究で提案した反応ネットワークは、分解生成物間の関係を説明しました。実験とモデル計算の比較を行い、各反応の特徴を示しました。結果は、亜臨界条件および超臨界条件においてラジカル反応が優勢であることを示しました。
2.「水素製造のための超臨界水ガス化におけるパーム油ミル排水(POME)ガス化の評価」
今日、オイルパーム産業の拡大は、大きな利点と欠点の両方を与えています。国民所得の源泉の他に、パーム油の生産はかなりの量の廃棄物副産物を得ます。最も困難な問題の1つは、パーム油工場排水(POME)です。本研究では、POMEの超臨界水ガス化の特性を25MPaの一定圧力で連続反応炉で調べました。ガス収量および組成、炭素ガス化効率(CGE)に及ぼす温度(500-600℃)および滞留時間(1-50s)の影響を調べました。結果は、より高い反応温度およびより長い滞留時間が、POMEの炭素ガス化効率を高め、より高い水素収率をもたらすことを示しました。
【講習会】 ≪バイオマス資源≫
講演:広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
エネルギー資源の枯渇が問題視されているなか、太陽エネルギーを使って生物が作り出すバイオマス資源は、再生可能エネルギーとして風力・太陽光などの自然エネルギーとともに注目されています。バイオマス資源には、乾燥系から含水系まで、また廃棄物系から生産系まで幅広いものがあります。今回のイブニングセミナーでは、バイオマス資源について、講習会という形式で紹介します。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
第68回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第41回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2018年10月25日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 D3 Apip AMRULLAH
「亜臨界水条件下における下水汚泥のガス化特性」
亜臨界水中のガス化下水汚泥を連続流反応器で調べました。 連続式反応器を使用し、温度を300および350℃で変化させ、滞留時間を5〜30秒間、25MPaの固定圧力で実験しました。 生成ガスの組成に対する温度および時間の影響を調べました。 ガス状生成物は、熱伝導率検出器(TCD)およびフレームイオン化検出器(FID)を備えたガスクロマトグラフ(GC)を用いて分析しました。 H2は、キャリアガスとしてN2を用いたGC-TCDによって検出されました。 HeガスをキャリアガスとするGC-TCDでCO2、COを検出し、HeをキャリアガスとしてGC-FIDによりCH4、C2H4、C2H6を検出しました。 その結果、ガス状の生成物は主としてH2およびCO2を含み、CH4およびC2H4の量は少なく、COは見出されませんでした。 温度は炭素ガスの効率に影響を及ぼしませんでした。
講演 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 機能化学研究部門
バイオベース材料化学グループ 主任研究員 花岡 寿明
「合成ガスを経由するリグニンから1,3-ブタジエン合成プロセスのシミュレーションと評価」
合成ガスを経由するリグニンからの1,3-ブタジエン合成プロセスを3つ提案しました。これらのプロセスは、合成ガスからn-ブテンを合成するルートを含んでおり、(1)直接合成、(2)ジメチルエーテル(DME)経由、(3)メタノール経由、という点で異なります。プロセスシミュレーションにより生成物収率、投入エネルギー、およびプロセスの利益(収支)を算出しました。その結果、DMEを経由するプロセスが最も高い収支が得られました。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
国際ワークショップ「1st Joint Workshop for efficient utilization of renewable bioresources」を開催しました
第一回 再生可能生物資源の効率的利活用に関わるジョイントワークショップ(広島大学ADSM, HU-ACE, インドネシアBalittas)
1st Joint Workshop of ADSM, Hiroshima University and Balittas, Indonesia for efficient utilization of renewable bioresources
日時:2018年10月22日(月) 13:00〜17:00
場所:広島大学大学院先端物質科学総合研究棟4F 401N講義室(https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/higashihiroshima/map_higashihiroshima)
お問合せ先:中島田豊(広島大学ADSM 教授, HU-ACE幹事, バイオマスプロジェクト研究センター幹事):nyutaka@hiroshima-u.ac.jp
主催:広島大学大学院先端物質科学研究科、共催:広島大学エネルギー超高度利用拠点(HU-ACE)、広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
講演内容
13:00-13:05: Opening remarks:
Prof. Junichi Kato, Dean of ADSM, Hiroshima University (tentative)
13:05-13:35: Dr. Mochammad Cholid, Dean of Balittas: Research and development program of Balittas
13:35-14:05: Dr. Marjani, Balittas: Breeding program on fiber crops with special emphasized on bast and leaf fiber crops
14:05-14:35: Prof. Nurindah, Balittas: Biological control of crop pests: roles of semiochemicals on tritrophic interactions and development of parasitoid attractants
14:35-15:00: COFFEE BREAK
15:00-15:30: Prof. Yukihiko Matsumura, HU-ACE, Hiroshima Univ.: Research activity of HU-ACE and recent progress of hydrothermal treatment of biomass. (tentative, under negotiation)
15:30-16:00: Assist. Prof. Kenshi Watanabe, ADSM, Hiroshima Univ.: Valuable oil production from various biomass by Aurantiochytrium (tentative)
16:00-16:30: Assist. Prof. Takahisa Tajima, ADSM, Hiroshima Univ.: Efficient production of biochemicals with simple biocatalyst using psychrophilic microorganisms (tentative)
16:30-17:00: General Discussion and concluding remarks
Prof. Yutaka Nakashimada, ADSM, Hiroshima Univ.
Financially supported by Advanced Core for Energetics Hiroshima Univ. (HU-ACE)
HU-ACEニュースレターVol.21 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.21 を発行しました。(Click)
広島大学工学部新第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) 発足記念シンポジウムを共催しました
広島大学工学部新第一類(機械・輸送・材料・エネルギー系) 発足記念シンポジウム
「輸送機器の研究・開発と教育のグローカル拠点を目指して」
日時:2018年9月28日(金)13:00~17:40 (開場12:30)
場所:広島ガーデンパレス2階 鳳凰の間
(広島市東区光町1丁目15-21)
詳細はこちらをご覧ください(Click)
シンポジウム「瀬戸内海を宝の海に~CREST最終報告とこれからの展開~」を共催しました
■■■シンポジウム「瀬戸内海を宝の海に~CREST最終報告とこれからの展開~」■■■
日時:2018年 9月 27日(木) 13:00~16:30
場所:サテライトキャンパスひろしま5階 504講義室(広島県民文化センター5階)
■講演会「瀬戸内海を宝の海に~CREST最終報告とこれからの展開~」
プログラム:
13:00-13:05 開会挨拶
中国地域バイオマス利用研究会 会長 松村 幸彦
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター センター長 松村 幸彦
13:05-13:30 広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 中島田 豊
「世界の海をエネルギー生産工場に」
13:30-13:55 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
「高温高圧水中を用いたバイオマス処理」
13:55-14:20 広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 秋 庸裕
「ラビリンチュラを活用する多角的バイオリファイナリー」
14:20-14:30 休憩
14:30-14:55 広島大学大学院先端物質科学研究科 助教 田島 誉久
「海洋性低温菌を活用した効率的な物質変換触媒の構築」
14:55-15:20 広島大学大学院先端物質科学研究科 准教授 岡村 好子
「海洋細菌を用いた資源リサイクルの展望」
15:20-15:45 東京農工大学大学院工学研究院・生命機能科学部門 教授 中村 暢文
「海藻から電気エネルギーと有用化学物質を生産する」
15:45-16:15 総合討論
16:15-16:20 閉会挨拶
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター 副センター長 中島田 豊
司会:広島大学大学院先端物質科学研究科 助教 田島 誉久
参加費: 2,000円(中国地域バイオマス利用研究会会員) 3,000円(非会員)
主催: 中国地域バイオマス利用研究会
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点(広大ACE)
後援:中国経済産業局(予定)
中国四国農政局(予定)
連絡先:〒739-8527広島県東広島市鏡山1-4-1
広島大学大学院工学研究科機械システム工学専攻内
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
中国地域バイオマス利用研究会
TEL・FAX:082-424-5762
Mail:bprc@hiroshima-u.ac.jp
第67回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第40回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2018年9月26日(水)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部115講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
「グリシンの超臨界水ガス化における窒素挙動」
地球温暖化を抑制するために、化石燃料の代わりにバイオマスなどの再生可能エネルギー源からエネルギーを使用することが現在求められています。窒素化合物を含むタンパク質は常にバイオマスに存在するため、この研究では、超臨界水ガス化に置けるアンモニア回収およびガス生成を解明するためにグリシンが使われています。グリシンを選んだ理由は、グリシンはもっともシンプルなモデル化合物です。この実験は管型反応器が使われています。実験条件中は温度が390,420、450℃、滞留時間が5-60s、原料濃度が1wt%、圧力を25MPaに保ちます。超臨界水ガス化に置ける窒素の挙動とガス生成の温度と滞留時間の影響が解明されました。この実験によると、グリシン分解物における窒素化合物のほとんどがアンモニアおよびメチルアミンとして存在していました。この実験では、二酸化炭素、水素が主要な気体生成物でした。高温で少量のメタンが発生しました。
講演 山口大学創成科学研究科機械工学専攻 教授 田之上健一郎
「バイオマス充填層のトレファクションにおける炭化特性に関する研究」
本研究では、竹、ベイマツ、バークの3種類のバイオマスについて成分分析、高位発熱量測定、トレファクション中の熱物質移動測定を行いました。その結果、竹の高位発熱量が他のバイオマスに比べて大きくなり、Ts = 623 Kで最大の高位発熱量を持つことが分かりました。また、竹中に含まれるキシランの発熱反応により、セルロースの一部が分解してトレファクション中のガス生成量は定常値を持つことが分かりました。ベイマツ、バークのトレファクションに関しては、それぞれ、マンナンやリグニンの熱分解に支配されることが明らかとなりました。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
HU-ACEニュースレターVol.20を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.20 を発行しました。(Click)
HU-ACEニュースレターVol.19を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.19を発行しました。(Click)
第47回機械システム工学講演会(第39回広大ACEセミナー)が開催されました
第47回機械システム工学講演会
日時:2018年8月28日(火)14:00~15:30
場所:工学部A3-131
講演者:大久保 友雅 准教授
所属:東京工科大学大学院 サステイナブル工学専攻
題目:CFRPのレーザー加工に関する数値計算
HU-ACEニュースレターVol.18を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.18を発行しました。(Click)
HU-ACEニュースレターVol.17を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.17を発行しました(Click)
HU-ACEニュースレターVol.16を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.16を発行しました(クリック)
第66回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第37回広大ACEセミナー)が開催されました
■第66回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第37回広大ACEセミナー)が開催されました
(English announcement can be found in the latter half of this notice.)
日時 2018年 7月 23日(月)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
講演 広島大学大学院理学研究科 共同研究講座助教 岡崎 久美子
「微細藻類ナンノクロロプシスによるバイオ燃料生産」
微細藻類ナンノクロロプシスは、ディーゼル燃料として利用可能なトリアシルグリセロールを多量に蓄積するため、バイオ燃料生産の材料として注目されています。我々は藻類からのバイオ燃料製造の実現に向けて、最適培養環境導出の研究や、藻類のさらなる高性能化を可能にするゲノム編集技術の研究などを行っています。今回は、ナンノクロロプシスの特性についてや、培養条件最適化の取り組みの様子などを紹介します。
講演 広島大学大学院工学研究科 D3 Pattraporn CHANGSUWAN
「グアヤコールの超臨界水処理における反応速度解析」
グアヤコールのリグニンのモデル化合物としての超臨界水ガス化における滞留時間の15〜90秒の影響を温度600℃、圧力25MPaで調べました。グアヤコールの濃度は0.5重量%に固定し、チャー製品が滞留時間とともに増加する間に、全有機炭素の結果は減少しました。しかし、滞留時間は炭素ガス化効率に影響しませんでした。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
第103回 メカニカルシステムセミナー(第36回広大ACEセミナー)が開催されました
・日時:2018年7月5日(木)16:00~
・場所:広島大学 工学部110
・講演者氏名: Prof. Bjorn Hauback, Department Head
・所属:Physics Department, Institute for Energy Technology, Norway
・講演タイトル:Rare-earth borohydrides – Crystal structures and thermal properties
・講演概要:Metal borohydrides have been extensively investigated over the last years
both as potential hydrogen storage materials and as solid state electrolytes in Li-ion batteries.During the last years our interest has been directed to the synthesis and properties of transition metal- and rare-earth (RE) borohydrides with different metal atoms and in some cases with anion substitution. This work presents detailed studies of the crystal structures and thermal properties of RE-borohydrides. These compounds show a big structural variety with anion substation, polymorphism, difference in coordination numbers and multiple oxidation states. The thermal decomposition of the mixtures has been studied by in situ synchrotron radiation powder X-ray diffraction, thermogravimetric analysis / differential scanning calorimetry and temperature programmed desorption. Composites with RE-borohydrides and LiBH4/LiH could be cycled at relatively mild conditions
第522回 物性セミナー(第35回広大ACEセミナー)が開催されました
日時:2018年7月5日(木) 10:00-
タイトル:Neutron scattering and imaging methods – overview methods and possibilities
講演者:Prof. Bjørn C. Hauback, Institute for Energy Technology (IFE), Kjeller, Norway
概要:Neutron scattering is an important method for characterization of materials. Neutrons have several unique properties: (i) the scattering from light elements is similar to heavy elements in the periodic table; (ii) neutrons have a magnetic moment and unique for characterization of magnetic materials; (iii) neutrons penetrate far into many materials, and thus unique to study bulk properties and easy to use complex sample environments; and (iv) the scattering between neighboring elements and isotopes of same element can be very big. This presentation will cover different advantages of neutron scattering methods, different types of neutron-based instrumentation and examples of applications.
IFE is running a reactor, JEEP II, that is used for neutron scattering. The present and coming instrumentation in our upgrade program, NcNeutron – Norwegian Center for Neutron Research (www.ncneutron.no), will be presented.
【国際シンポジウム】The 2nd International Symposium on Fuels and Energyを開催しました
第104回 メカニカルシステムセミナー(第38回広大ACEセミナー)が開催されました
第104回 メカニカルシステムセミナー(第38回広大ACEセミナー)が開催されました
題目:From the field to industrial product: Platform chemicals and materials from biomass
日時:平成30年6月19日(火)午前10:30~12:00
場所:広島大学東広島キャンパス工学部106講義室
要旨:Presentation prepared by Andrea Kruse, Dominik Wüst, David Steinbach, Paul Körner, Dennis Jung, Gero Becker
Fossil resources are limited and biomass is a valuable carbon resource.
Especially, if the preparatory synthesis work by plants can be used. Examples are the production of the platform chemical Hydroxymethylfurfural (HMF) and “n-doped” carbon materials.
HMF is a very interesting platform chemical, which can be transformed into other chemicals and consecutively to polymers.
This way e.g. a bio-based substitute for PET, called PEF can be produced.
At one of the farms belonging to the University of Hohenheim a bench-scale plant will be built-up to convert a lignocellulose, here Miscanthus, to HMF.
The Miscanthus grows also on one part of farm with marginal land. The idea is not to compete with food production; neither concerning the plant produced nor farm land.
Another on-farm concept bases on hydrothermal carbonization.
The hydrothermal carbonization of agricultural residues or other biomass types and the consecutive activation leads to interesting carbon materials.
These materials could be used to produce activated carbon, e.g. for hydrogen storage or the up-grading of biogas by carbon dioxide adsorption.
In addition materials for the use as electrodes in batteries or fuels cells, as well as supercapacitors can be produced.
Digestate based on manure fed biogas plants, is a very good feedstock.
With the Hohenheim process, MgNH4PO4, a good fertilizer can be produced, in addition to carbon material.
水素・次世代エネルギー研究会セミナー2017 Vol.2を共催しました
水素・次世代エネルギー研究会セミナー2017 Vol.2
-CO2フリー水素利活用への可能性を考える-
【日時】
平成30年2月20日(火) 13時30分~16時40分
【場所】
TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島4階)
【内容】
(1) 開会(13時30分~13時35分)
(2) 講演①(13時35分~14時25分)
「持続可能なエネルギー社会構築に向けた水素の貢献可能性」
講師 一般財団法人エネルギー総合工学研究所
プロジェクト試験研究部 副部長 飯田 重樹 氏
(3) 講演②(14時25分~15時15分)
「下水処理水と海水の塩分濃度差を利用した水素製造システム」
講師 地方独立行政法人山口県産業技術センター イノベーション推進センター
コーディネータ 上席化学工学技士 濵田 敏裕 氏
(4) 講演③(15時30分~16時10分)
「家畜ふん尿由来水素を活用した水素サプライチェーン実証事業の取組み」
講師 エア・ウォーター株式会社
産業カンパニー エンジニアリング事業部 担当部長 井上 知浩 氏
(5) 講評と総括(16時15分~16時40分)
広島大学 大学院工学研究科 機械物理工学専攻 教授 市川 貴之 氏
【主催】
水素・次世代エネルギー研究会
中国経済産業局
一般社団法人中国経済連合会
東広島市
広島市
公益財団法人広島市産業振興センター
広島大学【第26回 広島大学エネルギー超高度利用研究拠点セミナー】