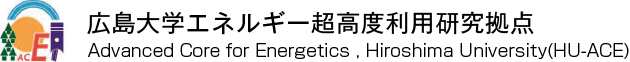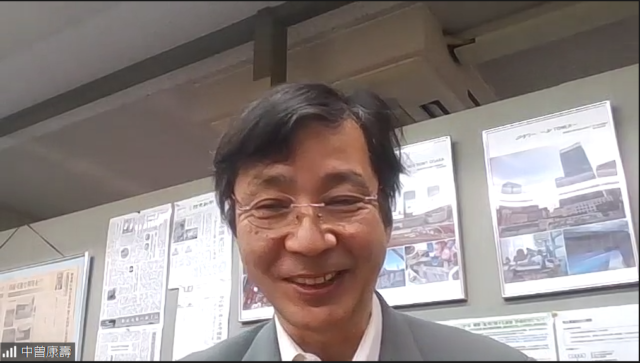■第106回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第119回広大ACEセミナー) のご案内
広島大学バイオマスプロジェクト研究センターと中国地域バイオマス利用研究会の共催で広島大学バイオマスイブニングセミナーを開催しています。バイオマスに関する基本的な考え方から最先端の情報までをカバーして、この地域におけるバイオマスの活動に資することを目的とするものです。第106回を以下の日程で開催しますので、ご参集下さい。
・日時 2023年4月24日(月)16:20~17:50
・開催形態 対面とオンラインのハイブリッド形式
・会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
広島大学までのアクセスについてはこちら
工学部の構内建物配置図についてはこちら
工学部の講義室の配置図についてはこちら
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 M2 井関 友洋
「グルコースの急速昇温型超臨界水ガス化管状反応器」
地球温暖化防止のため、バイオマス資源の活用が求められています。バイオマスの変換技術の一つに超臨界水ガス化があるが、低温域での固体生成物の発生によりガス収率が低下する問題があります。そのため、昇温速度を上げ、ガス化率を向上できると考えられています。本研究では、容積3.2mLのバッチ式反応器を誘導加熱により昇温してグルコースをガス化し、その昇温特性やガス収率を調べることを目的としました。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 D3 タボン リタヌパツプ
「セルロース、リグニンおよびキシロースの混合画分からの水熱炭化生成物の比較」
本研究では、セルロース、ヘミセルロース(キシロース)、リグニンの混合成分を様々な比率で280℃、0.5〜2時間HTC処理して得られたハイドロチャー生成物に着目した。その結果、セルロース-キシロース、キシロース-リグニン間の相互作用が質量生成物収量に影響を与えることが示された。また、ハイドロチャー生成物の特性について、粒径の観点から考察した。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 M2 リュウ ビョウ
「ピスタチオナッツ殻の水熱炭化反応」
化石燃料の使用により、多くの環境汚染が引き起こされているため、クリーンなエネルギーを見つける必要があります。 水熱炭化は、自然環境における石炭の形成過程をシミュレートすることができ、バイオマスをハイドロチャーに変換することができます。 本研究では、ピスタチオの殻を原料として、水熱炭化反応によりハイドロチャーに変換しました。反応温度、反応時間、原料比率を制御することで、ハイドロチャーの生成量を増加させるという目的を達成した。同時に、ハイドロチャーの特性を分析することで、応用の可能性を探っています。 現在、280℃でいくつかの試験を終えているが、反応滞留時間の増加に伴い、ハイドロチャーの生成量はまず増加し、次に減少し、反応滞留時間が60分のときにピークに達するという結論に達した。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 M2 井関 友洋
「スイカの皮のバイオチャーを触媒としたフルクトースの水熱液化」
地球温暖化防止のため、バイオマスの利用が求められています。ここでバイオマスの処理方法に水熱処理があり、5-HMFやレブリン酸を製造できる変換技術の一つです。この水熱処理では触媒を使用することがあり、安価で分離しやすい触媒が求められています。そこで、本研究では、スイカの果皮を熱分解して作ったバイオチャーを触媒として使用し、硫酸で処理したバイオチャーが最も反応を促進することが分かりました。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
参加希望の方へ
メールに、以下5項目(1-4は必須)を転記の上、件名に「イブニングセミナー参加希望」と記載の上、bprc@hiroshima-u.ac.jpまで、ご送付ください。
1.参加希望セミナー:4月24日開催、第106回バイオマスイブニングセミナー
2.お名前:
3.メールアドレス:
4.参加形態:□オンライン □対面
5.メッセージ: