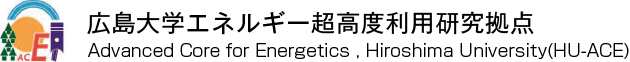皆様、広島大学バイオマスプロジェクト研究センターの活動に関していつもお世話になっています。ご存じの通り、私どもは原則として広島大学で月に1回イブニングセミナーを開催しています。
広島大学という立地の事情もあって、なかなか遠方の方に来ていただいてご講演いただくこともできなかったのですが、このたびの新型コロナウィルス対応で、ネット会議環境が整ってきました。特に、Zoom 利用者の増加により、遠隔会議を容易に開催することが可能になってきています。
私どもは、この機会を生かして、これまでご講演をお願いできなかったバイオマスを代表する先生方にお話を伺い、ディスカッションを行う機会を設けたいと考えました。ただし、資料の事前郵送や、講演いただく先生への謝金などを考慮して、従来とは異なり、参加費をいただいた形で、事前登録者に限って開催します。
通常の無料のバイオマスイブニングセミナーの何回かをプレミアムセミナーとし、その頻度は3ヶ月~半年に1回程度を想定しています。今回、第8回を2023年1月30日に企画しました。
第8回は株式会社PEO技術士事務所(Professional Engineering Office for Biomass (Peo-Bio Co.,LTD))代表取締役の笹内謙一様にご講演を頂きます。笹内様はわが国のガス化技術の第一人者であり、導入状況、課題、その対策などにもっとも通じておられます。わが国では、バイオマスの1カ所における発生量が小さいために、小規模でも高効率なガス化発電に対する期待が大きい状況でした。長年、タールの問題があって導入ができませんでしたが、欧州でタール問題を解決した小型ガス化炉が開発され、この数年で導入が進んできています。当初、欧州のバイオマスではうまくいくものの、国内ではトラブルが頻発するといった状況もありました。これについては、添加剤などによって解決が示され、導入装置数も大きくなっているようです。一方、FITの買い取り期間終了後の状況については懸念もあります。日本への小型バイオマスガス化発電の最新の状況をお話しいただきます。
以下の通りに開催します。是非ご参加いただければ幸いです。ディスカッションの時間も長めに取っています。意見交換の場としてもご活用ください。
日時:2023年1月30日(月) 16:30-18:00
場所:ZOOM オンライン(参加登録者に講演当日直接ご連絡させていただきます。)
主催:広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
共同主催:中国地域バイオマス利用研究会、広島大学エネルギー超高度利用研究拠点
参加費:3000円(中国地域バイオマス利用研究会メンバーは無料)
参加申込サイト:
http://i-aeu.sakura.ne.jp/230130premium/reg.html
参加申込及び参加費振込締切日:2023年1月23日(月)
*資料は講演者の著作権保護を含めた拡散防止のために事前郵送とさせて頂きます。ご了承ください。参加費取り扱いはエネルギー高度利用研究会に委託しています。領収書は予稿原稿とともに発送します。
【プログラム】
司会・解説:広島大学バイオマスプロジェクト研究センター長 松村幸彦
16:30-16:35 解説
16:35-17:20 講演:
(株)PEO技術士事務所 代表取締役 笹内謙一
「ポストFITにおける木質バイオマス熱分解ガス化発電の技術的課題と対策」
2MW未満のFITを対象とした小規模木質バイオマスガス化発電の普及には目覚ましいものがあります。しかし実際はFIT下においても想定より低い稼働率が報告されおり、さらに太陽光や風力など無償の自然エネルギー源を対象としてる他の電源とは異なり、FIT買取期間終了後もバイオマス発電は燃料バイオマスを買取り続ける必要があります。結果、FITの優遇措置が消滅するとその事業継続はますます厳しくなります。ここでは、FIT終了後も小規模バイオマス発電が生き残るための技術的な課題と対策について、経済性も加味して考えたいと思います。
17:20-18:00 ディスカッション
【お問合せ先】
広島大学大学院先進理工系科学研究科機械工学プログラム内
中国地域バイオマス利用研究会
TEL : 082-424-5762
FAX: 082-422-7193
Email : bprc * hiroshima-u.ac.jp (注: *は半角@に置き換えてください)