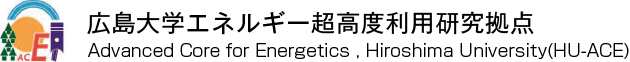「講習会:基礎からわかるバイオ燃料」
以下の通り、今年も「講習会:基礎からわかるバイオ燃料」を開催します。バイオ燃料について基礎からわかりやすく説明するとともに、最新の状況についても情報提供を行います。今回は、日本のガス化の第一人者である笹内様に小型ガス化のお話をいただきます。バイオ燃料に関する知識の整理や、バイオマス分野の新入社員の研修などにもご利用いただければ幸いです。
記
「講習会:基礎からわかるバイオ燃料」
主催:中国地域バイオマス利用研究会
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点(広大ACE)
日時:2020年 3月 16日(月)13:00~16:30
場所: サテライトキャンパスひろしま 5階 504講義室(広島県民文化センター5階)
広島県広島市中区大手町1丁目5−3
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pu-hiroshima.ac.jp%2Fsite%2Fsatellite%2F&data=02%7C01%7Cshu18%40hiroshima-u.ac.jp%7Cbff38c3b874847f4010908d7a65e1d06%7Cc40454ddb2634926868d8e12640d3750%7C1%7C1%7C637160795452299548&sdata=Bf93U8OOngoJYOgnKY8RrqNxH6bP1IoJ%2BFnkNljtArw%3D&reserved=0
※エディオン本館から南へ約100m
プログラム:
13:00-13:05 開会挨拶
中国地域バイオマス利用研究会 会長
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター センター長
松村 幸彦
13:05-13:45 広島大学 大学院先端物質科学研究科 教授 中島田 豊
「バイオメタン」
13:45-14:25 広島大学 大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
「バイオディーゼル」
14:25-14:35 休憩
14:35-15:15 県立広島大学 生命環境学部環境科学科 准教授 青栁 充
「ウッドペレット」
15:15-15:55 株式会社PEO技術士事務所 代表取締役 笹内謙一
「小型ガス化」
15:55-16:15 総合討論
16:15-16:20 閉会挨拶
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター 副センター長
中島田 豊
司会:広島大学 大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
参加費:
事前割引(3/5まで)
5,000円(中国地域バイオマス利用研究会会員) 8,000円(非会員)
当日
6,000円(中国地域バイオマス利用研究会会員) 10,000円(非会員)
参加申し込みサイト:
以下のサイトからお申し込みください。 (リンク)