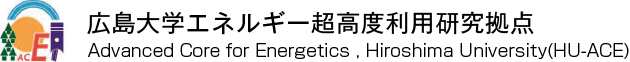■第59回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第24回広大ACEセミナー)が開催されました
(English announcement can be found in the latter half of this notice.)
日時 2017年 12月 6日(水)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
講演 広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 秋 庸裕
「海洋微生物を活用する油脂バイオリファイナリー」
海洋性微生物オーランチオキトリウムを利用して、食品産業廃棄物、生活・産業廃水、非可食草木類、大型藻類などの未利用バイオマスから、健康食品や医薬品となる高度不飽和脂肪酸、化粧品や養殖用飼料向けの需要が高まっている抗酸化カロテノイド、さらに化成品素材やバイオ燃料までを視野に入れて各種有用油脂を持続的に供給するバイオリファイナリー技術の確立をめざしています。本講演では、微生物育種を含む最近の進展を紹介します。
講演 広島大学大学院先端物質科学研究科 M2 宮本 翔太
「メタン発酵菌叢の油脂分解メカニズムの解明」
難分解性物質である高級脂肪酸に対して高いメタン生成活性を有する菌叢が当研究室で見いだされました。しかし、菌叢解析の結果、高級脂肪酸分解に関与する微生物は検出されず、複合微生物による分解が示唆されました。そこで本研究では、油脂分解メカニズムを明らかにするために、遠心分離処理や希釈法を用いた油脂分解活性に関与する微生物集団のスクリーニング法を検討しました。
講演 広島大学大学院工学研究科 M2 伊藤 大志
「水熱前処理におけるコンブ細胞の挙動」
コンブはマンニトールやアルギン酸など発酵可能糖を含む再生可能エネルギー資源として有用な物質です。しかしこのような有機物の多くはコンブの細胞内または細胞壁に含めれています。水熱前処理は細胞構造を破壊し有機物を取り出すことができます。コンブから適当に有機物を取り出すためには、コンブ細胞がどのような水熱条件下で破壊されるかの知見を得ることは重要です。しかし上記のような研究は未だ報告されていません。本研究ではコンブを、連続式試験装置を用いて水熱前処理しました。圧力、滞留時間は5 MPa、10分で固定し温度を110℃から130℃で変化させました。回収サンプルのうち液相は全有機炭素(TOC)分析、固相は光学顕微鏡を用いて観察しました。水熱前処理後、TOCの値は130℃において上昇しました。固体観察においても130℃における処理物のサンプルの細胞が破壊されていることが確認できました。以上の結果から、コンブの水熱前処理において130℃、5 MPa、滞留時間10分の条件はコンブ内の有機物を取り出すのに有効であることが確認できました。
司会 広島大学大学院工学研究科 研究員 Nattacha PAKSUNG