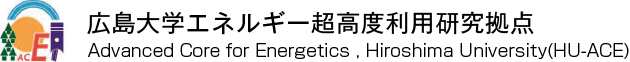HU-ACEニュースレターVol.29を発行しました。(Click)
Author Archives: AsanoHiroko
HU-ACEニュースレターVol.28 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.28 を発行しました。(Click)
第75回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第53回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2019年6月13日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部108講義
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 M2 横山 裕生
「微細藻類を用いた油排水処理」
マレーシアでのパームオイル産業は急速に発展していますが、この産業はその生産工程中で油を含んだ排水を大量に生産してしまうことが大きな問題となっています。この油排水を環境に優しく処理する方法が求められています。また、藻類バイオマスは,その特性からこの目的において有効に利用できる可能性があります。しかしながら、これまでに微細藻類を用いて油を取り除くと行った試みの報告はありません。そこで、今回の研究の目的を微細藻類がモデル油排水中の油除去に与える影響の確認としました。微細藻類のC. vulgarisをパーム油と水道水を乳化したモデル油排水中で培養しました。結果として、微細藻類が油排水中の油を除去できる可能性があることが示されました。
講演 広島大学大学院統合生命科学研究科 助教 渡邊 研志
「脂質代謝酵素の機能及び代謝ネットワークに関する研究と脂質発酵生産への応用」
脂質は食品、医薬品、燃料など多様な産業分野で重要な物質群です。特に微生物による油脂発酵は植物、魚、動物など従来の供給源からは大量取得が困難な脂質種の効率的生産が可能です。近年では環境問題などを背景に、バイオマスからの油脂発酵が注目されています。本口演では油糧微生物の脂質生合成反応を触媒する酵素の機能、それらの酵素が形成する代謝ネットワークの理解による生産脂質の多様化や生産性向上について紹介します。
講演 広島大学大学院工学研究科 D3 Rahmat Iman MAINIL
「超臨界水中におけるパーム油工場排水(POME)からの リンの回収」
インドネシアのパーム油生産からの廃液の量は、生産能力が増加するにつれて毎年増加しています。パーム油工場廃水(POME)中のリンは、過剰利用によるリン鉱石の枯渇を考慮すると、重要な潜在的リン資源となり得ます。超臨界水ガス化(SCWG)技術は、POMEをリン回収と共に来る価値あるガスに変換することができます。 SCWGでのPOME変換の動作についてよく理解するために、一連の実験が開発されました。ここでは、25MPaで圧力を制御しながら温度(500〜600℃)および滞留時間(5〜50秒)を変化させることを連続式反応器で用いました。 POME中の有機リンの無機リンへの変換の反応モデルも提案されました。その結果、有機蛍光体を無機リンに変換することができ、反応器内で沈殿が生じました。温度が高いほど速度は速くなりました。反応は一次速度論に従い、モデルは実験データとよく一致することがわかりました。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
第112回 メカニカルシステムセミナー(第54回広大ACEセミナー)を開催しました
■第112回メカニカルシステムセミナー(第54回広大ACEセミナー)
日時:令和元年6 月4 日(火)午後16:00~18:00
場所:広島大学東広島キャンパス工学部 A3-131
講師:Dr. Yangkyun Kim
Senior researcher, Fire Research Institute, Korea Institute of Construction and Building Technology, Korea
題目:Development of fire suppression technology in subsea tunnel and drone technology for detection of hazardous gases
要旨:
Numerical simulation on the water jet extinction system is carried out for systematical verification of its performance in subsea tunnel to enhance fire suppression performance. Numerical model applied is 2D Eulerian multiphase model, and its results is validated with the equation of motion and real-scale experiment. Simulation results show that volume fraction of water at all nozzle outlet pressures was less than 0.5. Also, water volume fraction on the ground of tunnel is increased according to an increase in jet discharge pressure in case of 0o of jet inclination angle, while water volume fraction on the ground of tunnel is decreased with an increase in jet discharge pressure in case of 5o and 11o of jet inclination angle. Gas detection test is carried out in open space through advanced open path infrared sensor (TOR sensor). In this study, chemometric method is applied to reduce interference in open space. Also, pyroelectric sensors and extra infrared lamps are applied to reduce its weight and size. The test is performed to detect gas concentration in 10 m with TOR sensor first in confined space, and real time gas detection test was successfully done eventually. Result shows that more than 0.9 correlation between supplied concentration and detected concentration by sensor. Eventually, real-time gas concentration in ppm is displayed on the geographical map to monitor gas safety.
第74回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第52回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2019年5月16日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部108講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 M1 小川寛太
「水熱反応場からの直接質量分析によるギ酸の確認」
水熱反応場は、水熱前処理、水熱炭化、直接液化、超臨界水ガス化など、各種のバイオマス変換に用いられる高温高圧の水反応場でありますが、その高い温度、圧力のために内部で進行する反応を確認することが容易ではありません。実際には生成物を急冷、減圧して回収、分析を行っていますが、この過程で反応がさらに進行したり、より安定な物質に変化してしまっている可能性も否定できません。しかしながら、現在のところ、サンプリングを行うことができる水熱条件は250 ℃までの低温に限定されています。これに対し、ニードルバルブを細かく制御することでより高温までサンプリングを行う水熱条件を広げられる可能性があります。しかしながら、これまでに250 ℃以上の反応場から直接サンプリングを行った検討例はありません。そこで、本研究では、ニードルバルブを導入し、400 ℃までの高温場からの直接サンプリングを行うことを目的とします。
講演 広島大学大学院統合生命科学研究科 D2 Mojarrad Mohammad
「Shewanella属細菌を用いた低温菌シンプル酵素触媒による3-ヒドロキシプロピオン酸と1,3-プロパンジオールの同時生産」
本研究では低温菌シンプル酵素触媒(PSCat)による3-ヒドロキシプロピオン酸と1,3-プロパンジオールの生産について検討を行いました。DhaB、DhaT、PuuCを発現させた低温菌を用いました。すべてのサンプルは酵素活性を評価する前に45℃、15分の熱処理を行いました。アルデヒドデヒドロゲナーゼ活性を測定したところ、NADH濃度が0.5もしくは1 mMの添加および40℃での反応で活性が見られました。また、DhaTを発現させた株でも同様の結果が得られました。現在、PSCatによる同時変換反応を評価しているところです。
講演:広島大学大学院統合生命科学研究科 助教 田島誉久
「シンプル酵素触媒によるイタコン酸の生産」
シンプル酵素触媒は熱処理により宿主の代謝酵素を排除するとともに基質の膜透過性を向上させて変換酵素による効率的な変換を行う触媒です。このシンプル酵素触媒により、クエン酸からイタコン酸を生産するために中温性の2種類の酵素をShewanella属細菌に発現させ高収率でイタコン酸を生産しました。また、効率的な変換のために触媒の固定化や2種類の酵素を近接化させる取り組みを行っており、それらを含めて紹介します。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
Call for Abstract 国際シンポジウムInternational Symposium on Fuel and Energy 2019(ISFE2019)
国際シンポジウムInternational Symposium on Fuel and Energy 2019(ISFE2019)のご案内をさせていただきます。
今年も来る2019年7月8-10日に東広島芸術文化ホールくららにて招待講演、一般講演(口頭、ポスター)によるシンポジウムを開催いたします。
シンポジウムのテーマは効率的な内燃機関の開発、水素エネルギーの利用、バイオマス活用、2050年のエネルギー確保・利用に向けたシナリオについてです。
ISFEサイト:https://home.hiroshima-u.ac.jp/~isfe/isfe2019/にて、一般講演(口頭もしくはポスター)の受付を行っています。(締め切り:5月17日(金))
皆様ふるってご参加くださいますよう、お願いいたします。
記
日時: 2019年7月8~10日 9:30~
場所: 東広島市芸術文化ホールくらら小ホール
(懇親会7月8日18:30~:東広島市役所10階展望ロビー)
テクニカルツアー7月10日 J-Power竹原火力発電所、アヲハタ工場見学
Call for Abstract : https://home.hiroshima-u.ac.jp/~isfe/isfe2019/top-page/call-for-abstract/
問い合わせ先:広島大学エネルギー超高度利用拠点 ISFE2019事務局
(広島大学大学院統合生命科学研究科、中島田豊、田島誉久)
HU-ACEニュースレターVol.27 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.27 を発行しました (Click)
シンポジウム「講習会:基礎からわかるバイオ燃料」を共催しました
「講習会:基礎からわかるバイオ燃料」
主催:中国地域バイオマス利用研究会
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点(広大ACE)
後援:中国経済産業局
:中国四国農政局
日時:2019年 3月 28日(木)13:00‐16:30
場所: サテライトキャンパスひろしま 5階 504講義室(広島県民文化センター5階)
広島県広島市中区大手町1丁目5−3
プログラム:
13:00-13:05 開会挨拶
中国地域バイオマス利用研究会 会長 松村幸彦
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター センター長 松村幸彦
13:05-13:45 県立広島大学 生命環境学部環境科学科 准教授 青栁 充
「ウッドペレット」
13:45-14:25 広島大学 大学院工学研究科 教授 松村幸彦
「バイオディーゼル」
14:35-15:15 香川大学 創造工学部機械システム工学領域 教授 奥村幸彦
「ガス化」
15:15-15:55 広島大学 大学院先端物質科学研究科 教授 中島田 豊
「バイオメタン」
15:55-16:15 総合討論
16:15-16:20 閉会挨拶
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター 副センター長 中島田 豊
司会:広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
参加費:5,000円(中国地域バイオマス利用研究会会員) 8,000円(非会員)
第73回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第49回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2019年3月7日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 M1 藤原芳樹
「水熱条件下での下水汚泥からのカルシウムを用いたリンの回収」
リンは生命の活動に必須な元素ですが、近年リン資源の枯渇が懸念されています。そのため、新たなリン資源の獲得が必要であり、リンを多く含んでいる下水汚泥に注目が集まっており、処理方法として、有機物を短時間で分解できる水熱処理が期待されています。さらに、分解し、無機リンの状態になったリンにカルシウムを添加することによって、容易にリンを沈殿回収できる可能性があります。そこで、本研究では、カルシウムを用いてリンを水熱反応場から回収するため基礎的な検討を行うことを目的とします。
講演 広島大学大学院工学研究科 D3 Pattraporn CHANGSUWAN
「超臨界水中におけるグアヤコールの転換に及ぼす 反応器壁触媒の効果」
本研究では、超臨界条件下でのリグニンのモデル化合物としてのグアヤコールの生成物分布に及ぼす金属壁触媒の影響を調べました。 これを実証するために、グアヤコールのガス化のための触媒として作用する、Fe、Niおよび種々の金属を含有するステンレス鋼316反応器を使用しました。 実験は、600℃、25MPaで連続流反応器中で行い、反応器の異なる内径(2.17、4.35および9.40mm)を用いて滞留時間を90秒に固定しました。 結果は、TOC、固体、およびガスの炭素収率が反応器の内径によって影響されないことを示しました。
【講習会】 ≪システム≫
講演:広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
エネルギー資源の枯渇と地球温暖化が問題視されている中、太陽エネルギーを使って生物が作り出すバイオマス資源は、再生可能で炭素中立なエネルギーとして風力・太陽光などの自然エネルギーとともに注目されています。その利用に当たっては、資源・変換・システムの3つの観点からの議論が求められています。今回は、システムの観点でバイオマスを議論するときに求められる考え方をエネルギー、環境、経済を中心にお話しします。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
HU-ACEニュースレターVol.26 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.26 を発行しました (Click)
公開シンポジウム「地域と環境とエネルギー」 (第14回広大ACEシンポジウム)を開催しました
これまで、広島大学総合科学研究科では「地域と環境とエネルギー」をテーマに掲げ公開シン ポジウムを開催し、昨年度東広島市が認定された『バイオマス産業都市』に焦点を絞った議論も 行いました。前回は、バイオマス産業都市として実績のある真庭市の市長に基調講演をしてい ただきました。 今回は、人口20万人を抱える中核都市、大学を抱える文教都市、農村部を抱える中山間地域、 沿岸部を抱える水産地域という多様性を有する東広島市に焦点を絞り、市長の講演をベースに 地域、環境、エネルギーについて議論を深めたいと考えています。
【日時】
2019年3月6日(水) 13時~17時 (12時開場)
【場所】
東広島市市民文化センター アザレアホール
(参加費無料)
【主催】
広島大学大学院総合科学研究科
【共催】
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点、エコネットひがしひろしま
【後援】
東広島市
【プログラム】
詳細はこちらをご確認ください。
第72回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第48回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2019年2月7日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/access/lectureroom
https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/access/building
https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/higashihiroshima
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 D3 Apip Amrullah
「下水汚泥の亜臨界および超臨界水ガス化におけるリンの挙動」
下水汚泥は最終製品の1つであり、これもまたリン(P)のキャリアであり、廃水処理システムにおけるP回収のための重要な資源を表しています。 本研究では、連続式反応器を用いて、下水汚泥の亜臨界および超臨界水ガス化におけるリンの挙動を調べました。 連続式反応器を使用し、そして実験を種々の温度(300、350、500、および550℃)、滞留時間(5〜30秒)、および25MPaの一定圧力で実施しました。 反応後の液体試料中のリンを定量分析しました。 結果は、有機リン(OP)が超臨界水条件とより短い滞留時間(10秒)の下で無機リン(IP)にほぼ完全に変換されることを示しました。
講演 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
「水熱粉砕が組成変化に与える影響」
粉砕前処理、水熱前処理は安価で環境に良いバイオエタノール生産の前処理方法として知られています。また、これらの処理を同時に行うことで効果的に前処理を進めることができることが報告されています。しかし,この同時水熱粉砕前処理後に発生する液相に溶解している成分が何由来のものかについて調査した報告はまだありません。そのため、今回の研究の目的を同時水熱粉砕前処理による原料の組成変化に粉砕が与える影響の確認とし、ディスクミルのディスク間距離を0.5 mm、1.5 mmとかえて前処理を行った際に得られた固体試料の実験前と実験後の組成を調べました。その結果、0.5 mm, 1.5 mmどちらの条件でもリグニン、ヘミセルロースが減少しており、液相溶解成分はリグニン由来のものが多いことが示唆されました。また、粉砕の程度が組成に与える影響はほとんど確認されなかったことから、この前処理中では,水熱溶解が主に進んでいる可能性があることがわかりました。
【講習会】 ≪生物学的変換≫
講演:広島大学大学院先端物質科学研究科 教授 中島田 豊
エネルギー資源の枯渇が問題視されているなか、太陽エネルギーを使って生物が作り出すバイオマス資源は、再生可能エネルギーとして風力・太陽光などの自然エネルギーとともに注目されています。バイオマスの有効利用には、適切な変換を行って2次エネルギーにする必要があります。バイオマスエネルギーの変換には、1)物理的変換2)熱化学的変換3)生物化学的変換の3種類があります。今回のイブニングセミナーでは、バイオマスの生物化学的変換について紹介します。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村幸彦
HU-ACEニュースレターVol.25 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.25 を発行しました (Click)
第71回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第46回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2019年1月24日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院工学研究科 M2 橋本 壮侍
「水熱条件下における有機態リンの無機化・有機物のガス化特性」
近年のリン鉱石枯渇問題から下水汚泥などの廃棄物からリンを回収し、リン鉱石の代替資源として利用する研究が行われています。そこで,下水汚泥の処理方法の一つとして水熱処理が提案されていますが、水熱条件下での有機態リンの分解特性は明らかではありません。本研究では下水汚泥中の代表的な有機態リンの一つであるDNAを原料として水熱処理を行い、その無機化特性及びガス化特性を確認しました。その結果、200℃付近でDNAからリン酸が生成されました。
講演 広島大学工学部 B4 小川 寛太
「水熱反応場の直接質量分析」
水熱前処理は第二世代バイオエタノールの生産に関して、重要です。従って、前処理中に起こっている反応について知ることが必要となります。既往の研究ではDuangkaewらが、直接質量分析装置を使用することによって、これまで高温高圧で発見されていなかった物質を発見しました。それは水熱前処理の反応分析に効果的であることが分かります。しかし、ノズルスプレーでは、許容される圧力が限られました。本研究では、既往の研究より高温高圧での分析を可能とするためにニードルバルブを追加しました。
【講習会】 ≪熱化学的変換≫
講演:広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
エネルギー資源の枯渇が問題視されているなか、太陽エネルギーを使って生物が作り出すバイオマス資源は、再生可能エネルギーとして風力・太陽光などの自然エネルギーとともに注目されています。バイオマスの有効利用には、適切な変換を行って2次エネルギーにする必要があります。バイオマスエネルギーの変換には、1)物理的変換2)熱化学的変換3)生物化学的変換の3種類があります。今回のイブニングセミナーでは、バイオマスの熱化学的変換について紹介します。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
シンポジウム「日本の森林と小型ガス化炉の最先端」を共催しました
バイオマス関連部会・研究会合同交流会 シンポジウム
「日本の森林と小型ガス化炉の最先端」
主催 第18回バイオマス関連部会・研究会合同交流会
共催 広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点(HU-ACE)
協賛 化学工学会エネルギー部会バイオマス分科会
日本エネルギー学会バイオマス部会
バイオマス利用研究会
木質バイオマス利用研究会
日本木材学会バイオマス変換研究会
バイオインダストリー協会アルコール・バイオマス研究会
日時:2019年1月15日(火) 13:00~17:00
(意見交換会 17:00~18:00)
会場:広島大学工学部219講義室
プログラム
司会:松村幸彦(広島大学)
13:00~13:05
開会挨拶 松村幸彦(日本エネルギー学会バイオマス部会部会長)
13:05~13:35
各部会・研究会活動紹介
13:35~14:05
講演「日本の森林の活性化に向けて」
吉岡拓如(東京大学・大学院農学生命科学研究科・准教授)
14:05~14:35
講演「小型ガス化導入の初期から現状まで」
竹林征雄(NPOバイオマス産業社会ネットワーク・副理事長)
14:35~15:05
講演「超小型木質バイオマス発電設備Volter40も紹介並びに稼働状況について」
駒田忠嗣(VOLTER JAPAN合同会社・営業統括責任者並びにVOLTER秋田・ 代表取締役)
15:05~15:15
休憩
15:15~15:45
講演「木質ペレット製造とブルクハルト社木質ペレットガス化熱電併給装置」
中川秀樹(三洋貿易株式会社・機械・環境事業部理事)
15:45~16:15
講演「ホルツエナジーCHPの日本普及」
三村和壽(株式会社バイオマス利活用技術舎・代表取締役)
16:15~17:00
ディスカッション「日本の森林とガス化の展望」
HU-ACEニュースレターVol.24 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.24 を発行しました。(Click)
HU-ACEニュースレターVol.23 を発行しました
HU-ACEニュースレターVol.23 を発行しました。(Click)
水素シンポジウム「水素の地産地消とビジネスモデル」を開催しました
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点
水素シンポジウム「水素の地産地消とビジネスモデル」
日時:2018年 12月19日(水)13:00~17:00(意見交換会 17:00~18:00)
対象:一般の方。
会場:TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前 ホール7A
JR山陽本線 広島駅 南口 徒歩2分
広島県広島市南区大須賀町13-9ベルヴュオフィス広島
https://www.kashikaigishitsu.net/facilitys/gcp-hiroshima-ekimae/
講演者・司会・プログラム:
司会:松村 幸彦(広島大学)
講演
13:00~13:05
開会挨拶 西田恵哉(広島大学エネルギー超高度利用研究拠点代表)
13:05~13:35
講演「水素エネルギーの基礎と展望」市川貴之(広島大学・教授)
13:35~14:05
講演「バイオマスからの再生可能水素製造」松村幸彦(広島大学・教授)
14:05~14:15
休憩
14:15~14:45
講演「水素社会に向けたPEM系電解技術の最新動向」
熊谷直和(日立造船株式会社・執行役員)
14:45~15:15
講演「太陽電池・水電解による高効率再エネ水素製造と国際流通の可能性」
杉山正和(東京大学・教授)
15:15~15:45
講演「エネルギー地産地消に向けた水素を核とした道筋」
古山通久(物質・材料研究機構・ユニット長/信州大学・教授/広島大学・客員教授) 15:45~17:00
ディスカッション「地産地消の水素戦略」
意見交換会
17:00~18:00 カンファレンスルーム7B。
連絡先:お問い合わせは以下のアドレスまでお願いします。
hu-ace-info@ml.hiroshima-u.ac.jp
第70回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第44回広大ACEセミナー)を開催しました
日時 2018年12月 6日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院先端物質科学研究科 准教授 廣田 隆一
「遺伝子組換え微細藻類の安全な屋外培養のための研究」
遺伝子工学技術の発展によって、有用な組換え微細藻類を作り出すことが可能になってきていますが、生物多様性に対する懸念から組換え体の利用は物理的に封じ込められた環境に限られています。私達は、生物の必須元素である「リン」の代謝経路を改変し、亜リン酸という化合物に生育を依存させる技術を開発しました。この方法は、高い効果と汎用性、経済性を兼ね備えており、実用的な組換え体の拡散防止技術として期待されます。
【講習会】 ≪物理的変換≫
講演:広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
エネルギー資源の枯渇が問題視されているなか、太陽エネルギーを使って生物が作り出すバイオマス資源は、再生可能エネルギーとして風力・太陽光などの自然エネルギーとともに注目されています。バイオマスの有効利用には、適切な変換を行って2次エネルギーにする必要があります。バイオマスエネルギーの変換には、1)物理的変換2)熱化学的変換3)生物化学的変換の3種類があります。今回のイブニングセミナーでは、バイオマスの物理的変換について紹介します。
司会 広島大学大学院工学研究科 教授 松村 幸彦
水素・次世代エネルギー研究会セミナー2018 Vol.1 を共催しました
水素・次世代エネルギー研究会セミナー2018 Vol.1
-水素社会実現に向けた課題!そしてその可能性は-
【日時】
平成30年11月21日(水) 13時30分~16時40分
【場所】
TKPガーデンシティPREMIUM広島駅前
(広島市南区大須賀町13-9 ベルヴュオフィス広島3階)
【主催】
水素・次世代エネルギー研究会
中国経済産業局、一般社団法人中国経済連合会、東広島市、広島市、
公益財団法人広島市産業振興センター、公益社団法人中国地域創造研究センター、
広島大学【第43回 広島大学エネルギー超高度利用研究拠点セミナー】
【プログラム】
13:35-14:15: CO2フリー水素社会の実現を目指して
広島大学 大学院工学研究科 機械物理工学専攻 教授 市川貴之
14:15-14:55: 旭化成におけるCO2フリー水素製造に関する取組み
旭化成株式会社 クリーンエネルギープロジェクト エネルギーシステム開発部 部長 白井健敏
15:10-15:50: 純水素燃料電池システムと統合管理システム
東芝エネルギーシステムズ株式会社 エネルギーシステム技術開発センター 室長 佐藤純一
15:50-16:20: 水島発電所2号機でのアンモニア混焼試験の結果と今後
中国電力株式会社 エネルギア総合研究所 マネージャー 谷川博昭
16:20-16:40: 講評と総括
広島大学 大学院工学研究科 機械物理工学専攻 教授 市川貴之