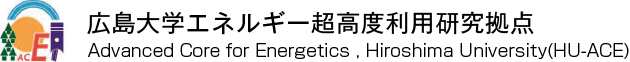開催報告はこちら
Author Archives: AsanoHiroko
【2024/5/9開催】第136回メカニカルシステムセミナー(第138回広大ACEセミナー)を開催します
開催案内はこちら
【2024/5/9開催】第135回メカニカルシステムセミナー(第137回広大ACEセミナー)を開催します
開催案内はこちら
釜山大学Humanoid olfactory display research centerと国際交流協定(MOU)を締結しました。
2024年2月28日に、当拠点と釜山大学ヒューマノイド嗅覚ディスプレイ研究センターで研究活動に関する国際交流協定(MOU)を締結しました。
釜山大学のヒューマノイド嗅覚ディスプレイ研究センターは、嗅覚ディスプレイ技術開発に関する研究を先進的に進めており、この度さらなるエネルギー分野における新たなセンサー開発などの課題と研究の発展のため大学間協定について協議し、今回のMOUが実現しました。今後の研究と教育交流がますます楽しみです。
【2024年5月23日開催】第114回バイオマスイブニングセミナー(第136回広大ACEセミナー)のご案内
案内はこちら
【2024年5月22日開催】第7回地中熱セミナー(第132回広大ACEセミナー)を開催します。
【2024年4月18日開催】第113回バイオマスイブニングセミナー(第134回広大ACEセミナー)のご案内
第113回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第134回広大ACEセミナー) のご案内
広島大学バイオマスプロジェクト研究センターと中国地域バイオマス利用研究会の共催で広島大学バイオマスイブニングセミナーを開催しています。バイオマスに関する基本的な考え方から最先端の情報までをカバーして、この地域におけるバイオマスの活動に資することを目的とするものです。第113回を以下の日程で開催しますので、ご参集下さい。
■日時 2024年4月18日(木)16:20~17:50
■会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
■参加形態 オンライン、対面(対面希望の場合は以下会場を参照、オンラインの方は必ず末尾のメールアドレスで参加申込をおねがいします)
広島大学までのアクセスについてはこちら
工学部の構内建物配置図についてはこちら
工学部の講義室の配置図についてはこちら
■プログラム■
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 NPO法人農都会議事務局長、バイオマスアカデミー幹事 山本 登
「木質バイオマス熱利用の現状分析と、日本としてどうすべきかの提案」
バイオマス熱利用は、日本の再生可能エネルギー戦略の重要な要素です。ゼロカーボン政策と連携し、エネルギー需要の約50%を占める熱源としての潜在力を持つ。しかし、欧米と比較して日本ではバイオマス熱利用が主流ではなく、技術的な遅れが見られる。木質バイオマスの安定した価格と信頼性の高い技術、地域経済への貢献、環境保護への効果は大きいが、日本のバイオマス熱利用に対する知識レベルの低さ、日本と外国先進国(欧州、中国、韓国)との住宅建設基準・エネルギー基準の違いが拡大の障害となっている。一方で、日本独特のバイオマス熱利用の拡大なども見られる。農都会議・バイオマスアカデミーの設立は、知識普及、技術レベルの向上、国産化、技術者教育活動を通じて、この分野の発展を目指している点についても紹介します。
講演 バイオマスアカデミー幹事 山本 登(黒坂事務所代表 黒坂俊雄様代理)
「木質バイオマス熱利用の意義と普及拡大の技術的なボトルネック」
再エネ熱利用に関して、欧州ではバイオマスが大きな割合を占めるのに対して、日本ではバイオマス熱利用は非常に少ない状況です。日本でも木質バイオマス燃料は発電に活用されていますが、発電効率は25%程度と低いです。ベース電源として木質バイオマス発電は意義を持ってはいますが、電力が最も不足するのは冬場の暖房・給湯ニーズへの対応です。低効率のバイオマス発電の電力で高効率ヒートポンプを駆動して熱需要対応するよりも、簡易で小規模分散のバイオマスボイラー熱利用の方に、効率面でも、経済面でも、社会システム面でもメリットがあるのではないかと思われます。日本でバイオマス熱利用が進まない理由は様々挙げることができますが、その中で、多くの人が気づいていない、技術的な側面や過去からの設計慣習についても、指摘したいと思います。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
■参加希望の方へ
メールに、以下5項目(1-4は必須)を転記の上、件名に「イブニングセミナー参加希望」と記載の上、bprc@hiroshima-u.ac.jpまで、ご送付ください。
1.参加希望セミナー:4月18日開催、第113回バイオマスイブニングセミナー
2.お名前:
3.メールアドレス:
4.参加形態:□オンライン □対面
5.メッセージ:
第6回地中熱セミナー(第132回広大ACEセミナー)を開催しました。
第112回バイオマスイブニングセミナー(第131回広大ACEセミナー)を開催しました。
開催報告はこちら
【2024年2月5日開催】第112回バイオマスイブニングセミナー(第131回広大ACEセミナー)のご案内
■第112回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第131回広大ACEセミナー) のご案内
広島大学バイオマスプロジェクト研究センターと中国地域バイオマス利用研究会の共催で広島大学バイオマスイブニングセミナーを開催しています。バイオマスに関する基本的な考え方から最先端の情報までをカバーして、この地域におけるバイオマスの活動に資することを目的とするものです。第112回を以下の日程で開催しますので、ご参集下さい。
日時 2024年2月5日(月)16:20~17:50
参加形態 オンライン、対面(対面希望の場合は以下会場を参照)
会場 広島大学東広島キャンパス 工学部112講義室
※いつもと違う講義室なのでご注意ください。
広島大学までのアクセスについてはこちら(https://www.hiroshima-u.ac.jp/access/higashihiroshima)
工学部の構内建物配置図についてはこちら(https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/access/building)
工学部の講義室の配置図についてはこちら(https://www.hiroshima-u.ac.jp/eng/access/lectureroom)
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学工学部 B4 古田 健
「バイオディーセル生産用カーボンナノチューブ担持酸化亜鉛触媒」
従来のバイオディーゼル合成では,塩基性均一系触媒を用いてメタノールと油を反応させるため,廃水処理や石鹸の生成など様々な問題がありました.これらの問題を回避するため,超臨界メタノールを用いて無触媒でエステル交換を行う方法が採用されましたが,高温高圧のため反応器が高価になるという問題がありました.この問題を解決するために,酸化亜鉛をカーボンナノチューブに担持した触媒を開発し,反応器の小型化と低コスト化を図りました.
講演 広島大学工学部 B4 児玉 瑞樹
「超臨界水中でのRu/CNT触媒によるグルコースガス化効率の向上」
超臨界水ガス化(SCWG)は、バイオマスを効率的に有用なガスに変換する有望な技術である。我々の以前の研究では、0.5 wt% RuをCNTに担持した触媒が良好な性能を示し、25 MPa、600℃で完全なガス化を達成した。液体およびガス生成物は、それぞれ全有機炭素(TOC)およびガスクロマトグラフィー(GC)によって分析された。系全体で起こる反応について一次速度論反応モデル式を確立し、反応特性を明らかにした。
講演 広島大学大学院 先進理工系科学研究科 D3 モハメド アフメッド モハメド アリ
「超臨界水ガス化における触媒担体としてのカーボンナノチューブ」
バイオマスガス化は、木材、農場の残り物、または都市の廃棄物を合成ガスに変えるプロセスであり、これは一酸化炭素、水素、およびメタンの混合物です。特に超臨界水ガス化(SCWG)とともに、このプロセスは湿ったバイオマスに対して効率的であり、事前乾燥の必要がなくなります。炭素ナノチューブ(CNT)は、その構造のためにSCWGにおける触媒サポートとして有望です。ある研究では、SCWGのためのRu/CNT触媒が、モデルのバイオマス化合物であるグルコースの完全なガス化を達成したことが示されました。遅いCNT反応により、Ruナノ粒子は安定し、連続的なガス化をサポートしました。この研究では、均一および非均一反応も調査され、600°Cでより高い反応速度が明らかにされました。この温度でも短い滞在時間で完全なガス化が達成されました。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
参加希望の方へ
メールに、以下5項目(1-4は必須)を転記の上、件名に「イブニングセミナー参加希望」と記載の上、bprc@hiroshima-u.ac.jpまで、ご送付ください。
1.参加希望セミナー:2月5日開催、第112回バイオマスイブニングセミナー
2.お名前:
3.メールアドレス:
4.参加形態:□オンライン □対面
5.メッセージ:
【2024年3月7日・対面/オンライン・要申込】バイオマスシンポジウム「講習会:基礎からわかるバイオ燃料」を開催します
皆様、このたび、以下の日程でバイオマスシンポジウム(会場とオンラインのハイブリッド)を開催します。多くの方の参加をいただければ幸いです。
なお、会場とオンラインのハイブリッド開催とし、資料は事前郵送となりますので、広島までおいでいただく時間の取れない方でも参加をいただけます。また、このため事前登録と参加費支払をお願いすることになります。よろしくご了承のほどお願いします。
【日時】2024年 3月 7日(木)13:00~16:30
【開催形式】Zoomによるオンライン開催と対面によるハイブリッド開催
【場所】サテライトキャンパスひろしま 5階 504講義室(広島県民文化センター5階)
広島県広島市中区大手町1丁目5-3
※エディオン本館から南へ約100m
【参加費】
5,000円(中国地域バイオマス利用研究会会員) 8,000円(非会員)
【参加申し込みサイト】
以下のサイトからお申し込みください。
http://i-aeu.sakura.ne.jp/240307hosty/reg.html
【申込締切】
2月21日までに参加申込みと支払いをお願いします。
【プログラム】
13:05-13:45 広島大学 大学院統合生命科学研究科 教授 中島田 豊
「バイオメタン」
13:45-14:25 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
「バイオディーゼル」
14:25-14:35 休憩
14:35-15:15 県立広島大学 生物資源科学部 生命環境科学科 准教授 青栁
「ウッドペレット」
15:15-15:55 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 共同研究講座教授 遠藤 貴士
「ナノセルロース」
15:55-16:25 総合討論
16:25-16:30 閉会挨拶
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター 副センター長 中島田 豊
司会:広島大学 大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
【主催】
中国地域バイオマス利用研究会
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
広島大学エネルギー超高度利用研究拠点(広大ACE)
【後援】
中国四国農政局
中国経済産業局
【お問合せ先】
〒739-8527広島県東広島市鏡山1-4-1
広島大学大学院先進理工系科学研究科熱工学研究室内
広島大学バイオマスプロジェクト研究センター
中国地域バイオマス利用研究会
TEL:082-424-5762 FAX:082-422-7193
Mail: bprc@hiroshima-u.ac.jp
【2024年2月14日開催】第6回地中熱セミナー(第132回広大ACEセミナー)を開催します。
■第6回地中熱セミナー(第132回広大ACEセミナー) のご案内
地中熱セミナーは、広島大学エネルギー超高度利用研究拠点(HU-ACE)の主催で開催するものです。
カーボンニュートラルへの需要側の取り組みとして地中熱利用の推進に関する基本的な考え方から最先端の情報までをカバーして、議論を深めていくことを目的としています。
第6回は、名古屋大学 施設・環境計画推進室 特任教授 田中英紀 様と、鹿島建設株式会社 技術研究所 塩谷正樹 様にご講演を頂きます。
現在、田中様と塩谷様はNEDOプロジェクトにおいて、地中熱や大気熱、太陽熱などの再生可能エネルギー熱(再エネ熱)を最適活用するための熱源水ループによる新たなヒートポンプシステムの実証研究に取り組んでおられます。また、田中様は長年名古屋大学のキャンパス計画に従事され、現在は日本建築学会 環境工学委員会の建築設備運営委員会主査を務めておられます。塩谷様におかれましても、学会活動に加え、建築物における多種多様な省エネ技術の研究開発に取り組んでこられました。本セミナーでは、おふたりから、NEDOプロジェクトの実施状況をお話いただくとともに、建築設備や省エネ技術の専門家の立場から、今後の地中熱のさらなる発展につながる情報をご提供いただきます。
以下の日程で開催しますので、是非ご参集下さい。
日時 2024年2月14日(水)16:20~17:50
会場 オンライン
参加費 無料
《プログラム》
挨拶 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授 金田一 清香
講演 名古屋大学 施設・環境計画推進室 教授 田中 英紀
鹿島建設株式会社 技術研究所 塩谷 正樹
「SSHPを用いたループ式地中熱ヒートポンプシステムの実証評価」
熱源水ループを用いた水熱源ヒートポンプ(エアコンおよび給湯器)システムの概要と実証運転結果およびエネルギー性能評価の結果を紹介します。システムでは、熱源水ループの温度を維持するために、地中熱交換器(ボアホール)と天空熱源ヒートポンプ(SSHP)が利用されます。SSHPは大気熱および太陽熱の直接投入ならびにヒートポンプ運転が選択可能で、再生エネルギー熱を積極的に活用するシステムとして考案されたものです。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 准教授 金田一 清香
【参加希望の方へ】
メールに、以下4項目(1-3は必須)を転記の上、件名に「地中熱セミナー参加希望」と記載の上、bprc@hiroshima-u.ac.jpまで、ご送付ください。
1.参加希望セミナー:2月14日開催、第6回地中熱セミナー
2.お名前:
3.メールアドレス:
4.メッセージ:
第111回バイオマスイブニングセミナー(第130回広大ACEセミナー)を開催しました。
開催報告はこちら
■ひがしひろしまエネ・エコセミナー第8回、第9回のご案内
小学生高学年以上の一般の方を対象に、いろいろなエネルギーと環境の話題について広島大学や東広島市の専門家が説明します。クイズ大会も行います。全9回。興味のある回だけの参加でもかまいません。この機会に、エネルギーと環境の情報をアップデートしませんか。
次回は第8回 1月27日(土)、カーボンリサイクルのお話です。
場所:広島大学みらいクリエ(東広島市鏡山一丁目4番5号 バス停「大学会館前」周辺)
定員:30名(希望者多数の場合には抽選)
参加費:無料
プログラム:
14:00~14:05 開会
14:05~14:35 講演1
14:35~14:45 休憩
14:45~15:15 クイズ大会
15:15~15:25 休憩
15:25~15:55 講演2とディスカッション
15:55~16:00 閉会
主催:広島大学エネルギー超高度利用研究拠点
広島大学A-ESG研究開発センター
東広島市
※申し込み:以下のサイトから(各回ごとに申込が必要です)、氏名、連絡先などをお送りください。
第8回「二酸化炭素を集めて使う -カーボンリサイクル-」
1/27(土曜日)14:00~16:00 申込締切:1/20まで
第9回「広島大学の取り組み」
2/10(土曜日)14:00~16:00 申込締切:2/3まで
第12回バイオマスプレミアムイブニングセミナー(第129回広大ACEセミナー)を開催しました。
開催報告はこちら
サイトオープン:第8回燃料とエネルギーに関する国際シンポジウム(ISFE2024)
【2024年1月17日開催】第111回バイオマスイブニングセミナー(第130回広大ACEセミナー)のご案内
広島大学バイオマスプロジェクト研究センターと中国地域バイオマス利用研究会の共催で広島大学バイオマスイブニングセミナーを開催しています。バイオマスに関する基本的な考え方から最先端の情報までをカバーして、この地域におけるバイオマスの活動に資することを目的とするものです。第111回を以下の日程で開催しますので、ご参集下さい。
日時
2024年1月17日(水)16:20~17:50
参加形態 オンライン・対面(対面希望の場合は以下会場を参照)
会場
当拠点が先進理工系科学研究科長特別賞を受賞しました!

【2023年12月19日開催】第12回バイオマスプレミアムイブニングセミナー(第129回広大ACEセミナー)のご案内
詳細はこちら
■ひがしひろしまエネ・エコセミナーを開催しています!
小学生高学年以上の一般の方を対象に、いろいろなエネルギーと環境の話題について広島大学や東広島市の専門家が説明します。クイズ大会も行います。全9回。興味のある回だけの参加でもかまいません。この機会に、エネルギーと環境の情報をアップデートしませんか。
次回は第6回 11月25日(土)、太陽電池のお話です。
場所:広島大学みらいクリエ(東広島市鏡山一丁目4番5号 バス停「大学会館前」周辺)
定員:30名(希望者多数の場合には抽選)
参加費:無料
プログラム:
14:00~14:05 開会
14:05~14:35 講演1
14:35~14:45 休憩
14:45~15:15 クイズ大会
15:15~15:25 休憩
15:25~15:55 講演2とディスカッション
15:55~16:00 閉会
主催:広島大学エネルギー超高度利用研究拠点
広島大学A-ESG研究開発センター
東広島市
※申し込み:以下のサイトから(各回ごとに申込が必要です)、氏名、連絡先などをお送りください。
第6回「太陽の光でクリーン発電 -太陽電池ー」
11/25(土曜日)14:00~16:00 申込締切:11/18まで
第7回「地上の太陽は実現できるか -核融合-」
12/16(土曜日)14:00~16:00 申込締切:12/9まで