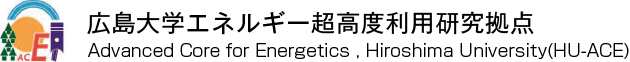■第86回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第70回広大ACEセミナー)を共催しました
(English announcement can be found in the latter half of this notice.)
日時 2020年7月13日(月)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 M1 宮迫 信之介
「水熱条件下における有機体リンの挙動」
水熱処理におけるホスファチジルコリンの無機化特性を確認することを目的に実験を行った。本研究においては,廃棄物系バイオマスに属する下水汚泥に主に含まれる有機体リンであるホスファチジルコリンを水に溶かし,1.0 wt%したものを試料として実験を行った。実験装置はSUS316製1/8インチ管および1/16インチ管から構成される連続式反応器を用い,滞留時間と反応時間の条件を変化させることで実験を行った。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 M1 田上 長
「水熱条件下におけるグリセルアルデヒドの反応挙動」
水熱処理は、バイオマスの前処理や有用物質の獲得など多様な用途を持つ点、水のみを用い環境に優しい方法である点などから注目を集めている。しかし、温度や圧力が変化すると水熱反応場で起こる反応や促進される反応も異なるため、温度や圧力が反応にどのような影響をもたらすかを知ることは重要となる。本研究ではグリセルアルデヒドを温度300 ℃、圧力15, 20, 25 MPaで1~40 s反応させて得られた気体生成物と液体生成物の分析を行い、反応速度定数を決定した。
講演 広島大学大学院工学研究科 M2 小川寛太
「水熱反応場の直接質量分析によるギ酸の確認」
水熱反応場は、水熱前処理、水熱炭化、直接液化、超臨界水ガス化など、各種のバイオマス変換に用いられる高温高圧の水反応場であるが、その高い温度、圧力のために内部で進行する反応を確認することが容易ではない。実際には生成物を急冷、減圧して回収、分析を行っているが、この過程で反応がさらに進行したり、より安定な物質に変化してしまっている可能性も否定できない。しかしながら、現在のところ、サンプリングを行うことができる水熱条件は250 ℃までの低温に限定されている。これに対し、ニードルバルブを細かく制御することでより高温までサンプリングを行う水熱条件を広げられる可能性がある。しかしながら、これまでに250 ℃以上の反応場から直接サンプリングを行った検討例はない。そこで、本研究では、ニードルバルブを導入し、400 ℃までの高温場からの直接サンプリングを行うことを目的とする。
講演 広島大学大学院統合生命科学研究科 M1 脇 滉
「河口底泥からの海洋性キチン分解菌叢の探索とVFAs生産」
キチンは、n-アセチルグルコサミンからなる多糖類であり、自然界においてセルロースに次ぐ二番目に豊富なバイオマスであることから、産業利用の可能性を持つ有望な再生可能資源である。しかし、不溶性なうえ、非常に硬度な構造を持つ難分解性ポリマーであるため、大腸菌や酵母などの一般的に工業利用されている微生物では分解ができない。そこで本研究では、効率的にキチンを分解し揮発性脂肪酸(VFAs)生産する海洋性キチン分解菌叢の探索と、その菌叢の性質についての検討を行った。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦