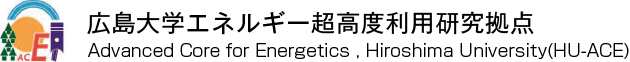HU-ACE ニュースレター Vol.48を発行しました(Click)
Author Archives: AsanoHiroko
第91回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第76回広大ACEセミナー) を共催しました。
第91回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第76回広大ACEセミナー) を共催しました。
日時 2021年1月12日(火)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院統合生命科学研究科 D2 竹村 海生
「遺伝子組み換えMoorella thermoaceticaを用いた合成ガスからの実用的エタノール生産プロセス開発に向けた検討」
当グループでは遺伝子組み換えMoorella thermoaceticaを用いた合成ガスからのエタノール生産に成功していますが、実用化に向け生産速度の向上が必要でした。そこで高菌体密度培養を試みました。高活性を維持した高濃度菌体調製法を用い菌体濃度を最大5.0g/Lまで高めたところ、培養容積あたりの生産速度は向上しましたが菌体あたりの生産速度は低下しました。低下の原因について、基質ガスの培地への供給速度の点から考察と検証を行ったので紹介します。
講演 岡山大学大学院環境生命科学研究科 教授 Md. Azhar UDDIN
「リグノセルロース系バイオマス由来タールの合成ガスへの接触水蒸気改質」
近年、石油資源枯渇によるエネルギー問題、および化石燃料の利用により排出される温室効果ガスCO2の増加による地球温暖化問題が深刻化しています。この問題の解決策の一つとして再生可能なバイオマスの有効利用が挙げられます。バイオマスの有効利用技術としていくつか挙げられますが、本研究では、木質(リグノセルロース)系バイオマスの利用技術の中でもガス化技術に着目し、ガス化過程で生成する揮発分(タール)の触媒による分解を目的とし、鉄‐セリウム系触媒の開発を進めました。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
HU-ACE ニュースレター Vol.47を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.47を発行しました(Click)
HU-ACE News Letter Vol.47
HU-ACE News Letter Vol.47was published. (Click)
【国際シンポジウム】The 4th International Symposium on Fuels and Energy を開催しました。
広島大学超高度エネルギー利用拠点では、2020年12月7-8日に国際シンポジウムISFE2020を開催しました。
*本シンポジウムはオンラインで開催いたしました。
第90回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第75回広大ACEセミナー) を共催しました。
第90回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第75回広大ACEセミナー) を共催しました。
日時 2020年12月1日(火)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
「バイオマス分野に関する共同研究の可能性/広島大学超高度エネルギー研究拠点の活動」
共同研究は必ずしも容易ではありません。これは、ある分野での常識がほかの分野ではそうではなく、自分が必要とするものがそのままの形で得られることは少ないためです。それでも、うまくいけばとても有効な成果を得ることができます。一つの事例として、広島大学超高度エネルギー研究拠点の活動を紹介します。2016年の設立以来、拠点のメンバーは各種のプロジェクトで共同研究を進めてきました。バイオマスに関しても、広島シナリオが描く分野のエネルギー研究者の相互理解に基づいて作られ、共同研究プロジェクトで外部資金を得ることにも成功しました。
講演 広島大学大学院工学研究科 D3 Pattraporn CHANGSUWAN
「超臨界水ガス化におけるグアヤコールからのチャー生成」
超臨界水ガス化(SCWG)は、再生可能エネルギーと廃棄物処理の相乗的応用を伴う適切な技術です。 しかしながら、副反応によって生成されたチャーの形成は、長時間の運転中に反応器の詰まりを引き起こし、プロセスにおける炭素ガス化効率を低下させます。本研究では、焼酎残渣(日本の蒸留液)を実際のバイオマスとして、グアヤコールをリグニンのモデル化合物として分解し、両方のタイプのバイオマスのガス化中の炭素生成物の収率と変換効率を予測しました。焼酎残渣とグアヤコールは、600°Cの温度と25MPaの圧力で連続フロー反応器で実施されました。 第一に、超臨界水ガス化反応器を設計するためには、実際の原料のガス化特性を決定することが常に必要です。湿った有機廃棄物のほとんどが固体と液体の成分で構成されていることを考えると、グアヤコール濃度(0.05〜1.0 wt%)と滞留時間(5〜94秒)が炭素生成収率とガス組成に及ぼす影響を調査した二次研究で、固形分は原料濃度の増加とともに増加しました。これは、固形分を生成する場合の1より大きい反応の順序を反映しています。 反応モデルを開発し、反応速度定数を決定して実験結果を再現することに成功しました。次に、グアヤコールと酢酸のようなラジカルとの相互作用が解明されました。酢酸は、SCWG条件下でグアヤコールからのラジカルチャー形成を阻害するための優れたラジカル捕捉剤であることがわかりました。相互作用パラメーターは、酢酸の添加が生成物の収率、特にチャーの収率に大きな影響を与えることを示しました。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
HU-ACE ニュースレター Vol.46を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.46を発行しました(Click)
HU-ACE ニュースレター Vol.45を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.45を発行しました(Click)
水素・次世代エネルギー研究会セミナー2020 vol.1を共催しました
水素・次世代エネルギー研究会セミナー2020 Vol.1
—水素利活用の課題と可能性を考える—
【日時】
令和2年11月17日(火曜日) 14時00分から15時30分
【開催方法】
Webexによるオンライン開催
【主催】
水素・次世代エネルギー研究会
中国経済産業局
一般社団法人中国経済連合会
東広島市
広島市
公益財団法人広島市産業振興センター
公益財団法人中国地域創造研究センター
広島大学【第74回 広島大学エネルギー超高度利用研究拠点セミナー】
HU-ACE ニュースレター Vol.44を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.44を発行しました(Click)
HU-ACE ニュースレター Vol.44を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.44を発行しました(Click)
第89回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第73回広大ACEセミナー)を共催しました。
■第89回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第73回広大ACEセミナー)を共催しました。
日時 2020年11月5日(木)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 B4 鎌形文佳
「メタノールを用いた竹からのカリウムの除去率」
竹は、成長速度が速く、燃焼の原料として期待されています。しかし、アルカリ金属含有量が高いため、その灰は低い温度で溶け、炉の円滑な運転を妨げます。竹を水で洗うとアルカリ金属を取り除くのに役立ちますが、得られる竹は水分含有量が高くなります。したがって、この研究では、乾燥工程の必要ない可燃性のメタノールを使用しました。目的は、メタノールを溶媒として使用した場合のカリウム除去率を決定することです。
講演 広島大学大学院工学研究科 M2 陳 百倫
「バイオマス微粉末の超臨界水ガス化」
超臨界水ガス化は、温度と圧力の両方が臨界点(647K、22.06MPa)を超える高温、高圧の水中でバイオマスをガス化します。 バイオマスは固体であり、気固または液固反応の観点から、粒子サイズの影響を考慮する必要があります。しかし、超臨界水中の固体バイオマスの挙動を予測するための十分な研究はありませんでした。この研究の目的は、固体粒子の超臨界水ガス化を実施して、粒子サイズ効果を決定することです。ステンレス管で作られた連続式反応器である実験室規模の反応器が採用されました。木質粒子と空果房の粒子を使用して、 さまざまな粒子サイズのサンプルを粉砕します。ガス化効率は粒度とともに低下することがわかり、超臨界水反応器にも気固反応や液固反応が存在するのと同様のメカニズムを示唆しています。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
「水熱液化排水に比較した超臨界水ガス化排水の藻の培養液としての優位性」
水熱液化や超臨界水ガス化のような藻の水熱処理は再生可能エネルギー生産システムとして注目を集めています。より進んだ再生可能性の実現ためには、これらのプロセス排水を藻の培養に用いることです。水熱プロセスの排水は藻に含まれていたカリウム、リン、窒素などの栄養分を含んでおあり、藻の培養に有効利用できます。 これまで、藻の水熱処理排水を藻の培養に利用するために、主に水熱液化の排水を利用して様々な研究がなされてきました。このときの問題点は、排水中の何らかの成分による藻の成長阻害でした。本研究では、異なる温度での超臨界水ガス化の排水を、通常の培地と混合して用いてみました。400 ℃の超臨界水排水は600 ℃のものより多くの不揮発性有機炭素を含んでいる以外は、ほかの栄養塩濃度はほぼ同じでした。しかしながら、藻の成長は600 ℃の排水の方が良好で、600 ℃における成長阻害物質の分解によるものと考えられました。
講演 広島大学大学院統合生命科学研究科 M2 小林駿介
「好熱性ホモ酢酸菌Moorella thermoaceticaのエタノール生産株におけるH2による増殖阻害の機構解明」
我々は糖やCO2を基質として利用することができる微生物Moorella thermoaceticaを代謝改変することでエタノール発酵生産プロセスの構築を試みました。従来の糖発酵プロセスではCO2が排出されてしまいますが、M. thermoaceticaを利用した発酵生産プロセスではCO2も炭素源として利用することが可能となります。CO2利用はH2によるエネルギーを必要としますが、取得した株は想定外なことにH2により増殖が阻害されました。そこで、この阻害機構を検討しましたので報告します。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
第6回公開シンポジウム「持続可能社会-里山とエネルギーと地域」を共催しました。
オンライン開催。
第6回公開シンポジウムポスター.pdf(Click)
HU-ACE ニュースレター Vol.43を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.43を発行しました(Click)
HU-ACE ニュースレター Vol.42を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.42を発行しました(Click)
第88回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第72回広大ACEセミナー)を共催しました
■第88回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第72回広大ACEセミナー)を共催しました。
日時 2020年10月5日(月)16:20~17:50
会場 広島大学東広島キャンパス工学部110講義室
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 M1 Sin Sokrethy
「カンボジアにおける農村発電プラントのためのバイオマス資源とする稲わらおよび籾殻」
カンボジアは人口の80%を稲作に依存している発展途上国である(国際協力機構(JICA)、2013年)。稲作農場からの毎年の廃棄物は、発電プラント設置の際の優れたバイオマス資源になると考えられる。本研究の目的は、残留物、稲わら、および籾殻の見積量を明らかにし、地理情報システム(GIS)に資源レベルを表示するために資源指標のインデックス(IIR)を使用することである。 もう1つの目的は、本研究対象地域である、ボンティアイミアンチェイ州、バッドムボン州、およびポーサット州における利用可能な資源による電力生産およびCO2排出量削減の可能性を明らかにすることである。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 準教授 Tran Dang Xuan
「メコン川下流域の農業及び漁業に対する本流における発電所の及ぼす影響」
本研究ではメコン川下流域の漁業、農業分野について議論し、カンボジア、ベトナム下流域の氾濫原に焦点を当てていく。メコン川下流域のダムの建設は、気候変動による損失よりも生物多様性と漁業面でより大きな損害を与える。カンボジアとベトナムでそれぞれ、漁獲量で276,847tと178,169tの減少、米の収穫量ではそれぞれ-3.7%と-2.3%、トウモロコシの生産量は-21.0%と-10.0%となり、これによりGDP成長率はカンボジアでは-3.7%、ベトナムでは-0.3%という結果になる。ラオスでは、予定されているダムの建設により、他のメコン川下流域諸国の中電力供給による利益が他のメコン川下流域諸国の中で最も大きいであろう。総漁獲高の減少が、ラオス、タイ、ベトナムでは3分の1にとどまる一方で、カンボジアは4分の3まで減少を強いられることになる。
講演 広島大学大学院先進理工系科学研究科 D3 Pattraporn Changsuwan
「超臨界水中におけるグアヤコールの変換に及ぼす異なる濃度の酢酸の添加効果」
有機ラジカルスカベンジャーである酢酸が、ラジカルスカベンジャーの濃度を変えることによる超臨界水ガス化におけるグアヤコールの変換に及ぼす影響を調べた。 グアヤコールと酢酸の混合物は、連続フロー反応器で、温度600℃、圧力25 MPa、グアヤコールの固定濃度0.5 wt%で実施した。 ラジカルスカベンジャーの濃度が低い場合、高分子量を形成するラジカル反応が減少したため、少量の固形生成物(チャーとタール)が生成された。 0.2重量%より高いラジカルスカベンジャーの濃度で固体生成物の量はゼロであったが、過剰量のラジカルスカベンジャーは中間化合物を形成し、ガス生成物に分解することを好む。 結果は、酢酸がラジカルによる高分子量構造の形成を阻害するため、酢酸がグアイアコールのガス化における固体形成を抑制するための重要なラジカル捕捉剤であることを示している。
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
第87回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第71回広大ACEセミナー)を共催しました
■第87回広島大学バイオマスイブニングセミナー(第71回広大ACEセミナー)を共催しました。
日時 2020年9月28日(月)16:20~17:50
会場 広島大学工学部 中会議室(A1棟1階141号室)
プログラム
解説 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
講演 広島大学大学院統合生命科学研究科 教授 中島田 豊
「合成ガス発酵によるカーボンリサイクル型化学品製造技術」
我が国の化学品の大半は石油由来の原料から製造されている.化学品原料は石油消費量の約23%を使用していることから,大量のCO2を排出している状況にある。このため、経済産業省はCO2排出量削減を目的として、2019年6月にカーボンリサイクル技術ロードマップを示した。この中で、CO2排出量削減に貢献する新しい化学品製造技術の開発が求められている.特に,プラスチック原料の中核となるC3, C4化学品の新規製造法の開発が求められている。バ イオマスや廃プラスチックをポリマーの原料とする手法として,合成ガスを中間物とした製造技術は合成ガスプラットフォームと呼ばれる。これまでに我々は合 成ガス発酵に注目した研究開発を進めてきた。合成ガス発酵とは、高価な触媒や有毒な触媒を使用せず、合成ガスを原料としてC2-C4化合物を生産できる微生物を用いたバルク化学品生産技術である。本講演では,我々が開発してきた合成ガス発酵技術の一部とともに,本技術によるカーボンリサイクルの可能性について紹介したい.
司会 広島大学大学院先進理工系科学研究科 教授 松村 幸彦
HU-ACE ニュースレター Vol.41を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.41を発行しました(Click)
HU-ACE ニュースレター Vol.40を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.40を発行しました(Click)
HU-ACE ニュースレター Vol.39を発行しました
HU-ACE ニュースレター Vol.39を発行しました(Click)